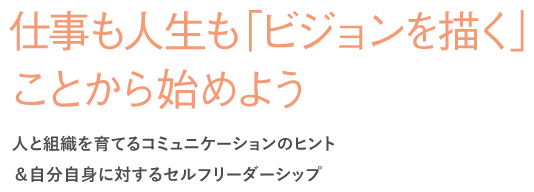理想のコーチへの道は、終わりのない旅のようなもので、進めば進んだだけ、先に奥があることが見えてきます。
常にコーチとしてブラッシュアップしていけるように私が定期的に紐解くのは、国際コーチング連盟が発行するコア・コンピタンシーや各マーカーです。
コア・コンピタンシーや各マーカーを大切にされているコーチの方はきっと多いですよね。
さて、そのコア・コンピタンシーの中から、その時々で気になっている文について、少しずつ綴っていきます。
最初は、C7 Evoke Awareness(気づきを呼び起こす)の定義の文について。

定義の文
Definition: facilitates client insight and learning by using tools and techniques such as powerful questioning, silence, metaphor or analogy.
「人を動かす質問、沈黙、比喩や類推などのツールやテクニックを用いて、クライアントの洞察と学習を促進している」 ーICF Japanの翻訳より引用
この文をわかりやすいように分解して表現すると、
「コーチはツールやテクニックを使って、クライアントの洞察や学習を促す。例えば、人を動かす質問、沈黙、メタファーやアナロジーを使って」
となります。
この文でわかりにくいのが、メタファーとアナロジーです。
辞書で調べてみると、
メタファーとは、「二つの全く異なるものを比較、または関連づける」 例)「時間はお金だ」
アナロジーは、「他の点では異なるもの同士の似ている点を関連づける」
とあります。
わかりやすいようにザクッと捉えると、「~だ」「~のような」というフレーズをツールとして使う、ということですが、
具体的にはどんな場合でしょう?
具体例
メタファー、アナロジーについて考えていたある時、コーチングの中で自然に使っていることに気づきました。
一気に組織を変えたいというクライアントに、
「リトマス試験紙って、じんわりと色が変わりますが、今、~さんはそのじんわりが待ってられない、そう感じておられるような気がしましたが、いかがですか?」と尋ねました。
そうしたら、その方はたまたま視覚優位な方だったので、
そのフィードバックでイメージが鮮明に頭の中で広がり、自分の状態にハッとされた様子でした。
クライアントの優位な感覚を知り、それを質問に活用する
このときのクライアントの様子に、加えて気づいたことがあります。
そして、これが結構大事なところだと感じているところですが、
それは、
「クライアントの得意なVAK(視覚、聴覚、体感覚)を把握して、それに合ったメタファー・アナロジーを使うとより効果的」
というものです。
視覚優位の方にはイメージが広がるようなメタファー・アナロジー、
聴覚優位の方には音、または言葉を有効に使ったメタファー・アナロジー、
例えば、「早く早くと耳元でゴングが鳴っているような感じですか?」など
体感覚優位の方には体で感じるメタファー・アナロジー
例えば、「いつも胸にモヤモヤとしたもどかしい雲があって、早くそれを取り除きたい感じですか?」 など
クライアントの優位な感覚をメタファー・アナロジーに使うと、よりクライアントの自己理解を深める助けになるのではと思います。
定義文だけでもよくよく考察すると、深いです。